 だれにもいわずにおきましょう。朝のお庭のすみっこで、花がほろりとないたこと。
だれにもいわずにおきましょう。朝のお庭のすみっこで、花がほろりとないたこと。
もしもうわさがひろがってはちのお耳へ入ったら、わるいことでもしたように、みつをかえしにゆくでしょう。
鬼門に向かって鬼瓦を置くことで邪気を跳ね除けるのと同様に、鬼を神として祀れば厄災から守ってもらえる。この村に住む人々は、そう信じていた。
一年の豊作を祈る祈念祭。そこでは例年、子どもが供物として鬼様に捧げられる。山を住処とする鬼様は、普段人々の前に姿を現さない。しかしこの祈念祭では、山から降りてきて、そうして村民の見守るなか生贄を喰らうのだ。
肉が裂かれ、骨が砕け、血が吸われる音。生きたまま喰われる苦痛に泣き叫ぶ生贄の声。五穀豊穣を祈って村人たちが奏でる太鼓や笛、念仏。そんな狂気的な混沌に満ちた祈念祭が、今年も近づいている。

或る村
「お父さん、お母さん、行って参ります」
恭しく頭を下げた娘、は、陽が落ちる前には帰ってくるようにと言う母に「はい」と返し、玄関の戸を開いた。立春とはいえ、朝晩はまだ凍てつくような寒さがしぶとく残る。頬を刺す外気に一瞬体を震わせただったが、キッと挑むような目で空を見上げると、一度深く息を吐き、そうして今度は大きく吸った。肺が凍るようだったが、その中で口内に感じたわずかな甘みに、春が確かにもうすぐそこまで来ているのだと知る。は頬を緩めると、大きく一歩を踏み出し、そのまま意気揚々と歩いていく。
父から「お前に家の者としての務めを一つ任せる」と告げられたのは、昨夜のことだった。明朝、山の麓にある神社へ向かえ。そこで待つ叔母と合流して、あとは叔母の指示に従え、と。
の足取りが軽いのは、父からひとつ認められた気がして、うれしかったからだ。は、この村の万事を取り仕切る家の養子として育てられた。生みの親の顔も、名前も、その消息も知らない。ただ、自分が家の実の子ではないということだけは知っていた。他の兄弟たちと自分は違う。両親はきっと自分に期待していない。そう諦めていたからこそ、今回こうして父から役目を授けられたことがとてもうれしかった。
「叔母さん!」
神社の境内に佇む叔母の姿に、は声を弾ませた。幼い頃からかわいがってくれた叔母に、はとても懐いていた。
叔母は両手に風呂敷や桶を抱えていたため、の呼び声に手を振って返すことはできなかったが、「待ってたよ」と明るく微笑んだ。
叔母のもとへと駆け寄ったは、「持つよ」と言って桶を取った。中には水がたっぷりと入っている。は水面に映った自分の顔を見つめながら訊く。
「今日は一体なにをするの?」
「家の人間としての大事なおつとめだよ」
「うん、それはお父さんからも聞いたんだけど、実際に何をするのかは教えてくれなくて……」
「まあ見ればわかるさ」
叔母はそう言うと、神社の裏手へ続く道へと進みながら「付いておいで」と言った。
の実の父親は、この村の生まれだった。彼はよその村出身の女を娶って子をもうけた。それがだった。生まれながらの色白で髪の色味も薄いを見た家の家長は、両親に告げた。差し出せ、と。娘が取り上げられそうになり、母親は抵抗した。父親も猛反発した。それも虚しく、娘は奪われ、二人は殺された。――その事実を、はもちろん知らない。自分がなぜ奪われたのか、なぜ齢十五になるまで何不自由なく育てられたのか。その理由も、知らない。
鬱蒼と生い茂った草を掻き分けながら歩く叔母の後ろに続いていただったが、風に乗って届いた臭いに顔をしかめた。鼻をつくような、鼻を根元からねじ曲げてくるような、そんな臭い。
叔母は不意に立ち止まると、地面を見おろす。そこには格子状の蓋があった。叔母がその蓋を持ち上げると、大人二人が入れるほどの穴が露わになる。途端に強くなった臭いに、は鼻を押さえた。叔母は別段顔色を変えることもなく、傍らに置かれていた梯子を穴の中へと入れ、するすると降りていく。はためらいつつもその後に続き、穴へと身を沈めていった。
梯子を降りた先には、湿気と臭気に満ちた洞窟が広がっていた。
「さあ行くよ。みんな待ってる」
そう言う叔母の声が反響する。みんな、とは。叔母は篝火に松明をかざして火を移すと、仄暗い道を照しながら進んでいく。踏み歩く足音の中に、それ以外の何かが聴こえてきたとき、は足を止めた。洞窟の行き止まり。そこには鉄製の牢があった。鉄格子の向こうに揺らめく小さな影に、は声を失う。叔母が牢屋を開けると、小さな影が松明のあかりに吸い寄せられるように近づいてくる。子どもだ。まだ年端もいかぬ子どもたちが、牢の中に押し込められていた。
「あ、あー、うぁ」
つんと引かれる感覚にが目をやれば、紅葉のような手が裾にぶら下がっていた。言葉にならない声を上げているその子どもは、ボロ布を身に纏い、髪は伸びきって、皮膚の至る所が黒く汚れていた。
「祈念祭の生贄。その面倒を見るのが、家の務めの一つでもあるんだよ」
は祈念祭に参加したことがなかったが、村の豊作のために鬼様へ捧げ物をするのだということは知っていた。その捧げ物がまさか、人間だったとは。
「ほら、体拭って食べ物をあげて。それは今年の生贄だから、特に丁重に世話しとくれよ。もう少し太らせたほうが鬼様も喜びそうだね」
叔母が「それ」と呼んだ子は、の裾を掴んだまま、絶句するをじいっと見上げていた。すると叔母は突然子どもを抱き上げ、
「あんまり目を合わせるんじゃないよ。情が移っちまうからね」
そう言って、水を含ませた手ぬぐいで体を拭きはじめるのだった。意味を成さない声を発しながら、他の子どもたちがの方へと近づいてくる。もう喋ってもおかしくないような子ですら、言葉を話せない。きっと生まれたときからここで、家畜のように育てられてきたのだろう。
「できるだろう。お前も家の人間なんだから」
あんなに優しかった叔母が、今は血の通わない別の生き物のように思えた。しかし叔母のその言葉に、ふと両親の顔が浮かんだ。――期待してもらえたんだ、やっと。裏切るわけにはいかない。
は奥歯を噛み締め、ごくりと唾を飲み込む。そうして叔母の持ち込んだ荷物から食糧を取り出すと、わらわらと集まってきた生贄の子らに分け与えはじめるのだった。
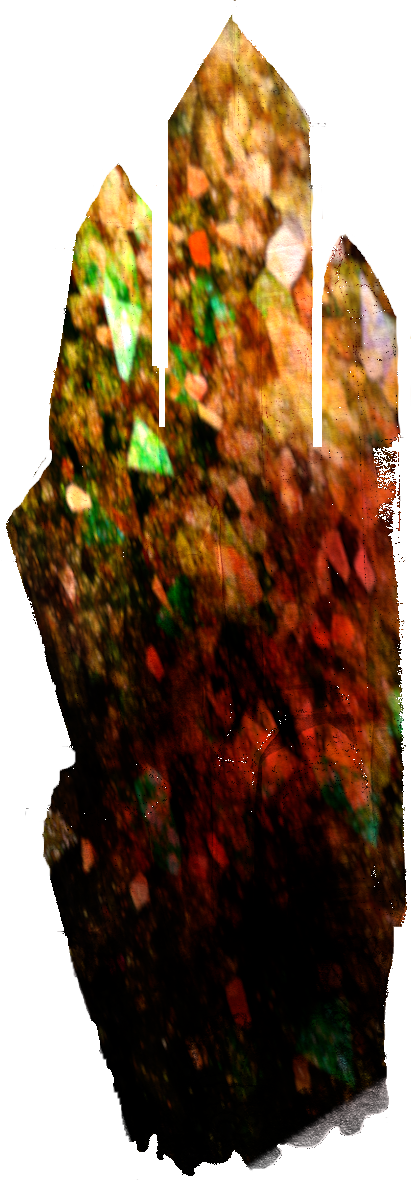
嫌な匂いがする。
鬼殺隊炎柱――煉獄杏寿郎は、歩みを止めて辺りを見渡した。葉を落とした木々以外には別段変わったものはない。煉獄はかすかに息を吐く。白い吐息は風にかき消されていく。そうして腰に差した刀の柄をギッと握ると、再び足を進める。
季節は山からおりてくるものだと思っていた。山頂に雪が積もれば、そのあと里にも雪が降り、山々が赤く燃えれば、里の紅葉もはじまる。けれどこの山は、他とは異なるように思えた。春立つ頃なのに、草花の息吹をひとつも感じないのだ。里の木々でさえ芽を結びはじめている。しかし、この山の木は寒々しい格好をしていて、まるで冬のまま刻が止まっているかのようだった。
煉獄がここにいる理由。それは、鬼の棲む山に向かった小隊が消息を絶ったためだ。小隊長の階級は乙。腕の立つ者だった。報せがないということは、戦闘不能の状態であるということ。
「生きていればいいが」
誰か一人でも。そうすれば、鬼の情報が掴める。隊員らの最期を聞き、それを遺族へ伝えられる。
煉獄はまた足を止める。曇天の空に向かって白い煙が上がっていた。あの下にはきっと民家があるはず。ここからもう一つ山を越えた辺りだ。何か鬼の手がかりを得られるかもしれない――。
「私が、お客人の?」
地下牢から戻ってくると、家中がざわめき立っていた。何事かと声のする方へと向かえば、裏庭には父と村の男衆が集い、何かを話し合っている様子だった。父はに気づくと、しっし、と追い払うように手を振った。
なんだったんだろう。肌にまとわりついた地下牢の臭いを洗い流し、もう今日は早く休もうと自室へ向かっていた時。呼び止められて振り向くと、そこには父と母がいた。そうして告げたのだ。「村に客人が来ている。今夜はこの家に泊まってもらうことにするから、お前が食事や布団の支度をしなさい」と。なかなか言葉を飲み込めずにいると、「何を訊かれても知らないと答えなさい」と母が言った。「力づくで何かされそうになったら大声で助けを呼びなさい」とも。
「御免ください」
腹に響くほどの力強い声に、父は眉根を寄せ、母は不快そうに目を細めた。「私たちが部屋へ案内するから、お前は食事を」と言って、父と母は客人の待つ玄関土間へと向かった。
「失礼いたします」
恐々と声を掛けると、襖の向こうから「どうぞ」と歯切れの良い声が返ってきた。ふう、と呼吸を整え、襖を少し開ける。その時なぜだか、あたたかな風が鼻先を過ぎていった。
「あの、夕食をお持ちしました」
手を突いて頭を下げれば、
「それはありがたい。どうぞ入ってください」
という返事が。ゆっくりと表を上げ、上目で客人を見やる。思わず声が漏れそうになるのを、は口に手を当てて抑えた。客人の髪が、見たことのないような色をしていたからだ。金色の頭髪に、毛先は燃えるような赤。とっさに、紅葉みたいだと思った。こちらを見る瞳も、まるで燭台の炎がそのままその中に棲みついているような。
「驚かせてしまいましたか。この髪や目は生まれつきで、先祖代々こういう容姿なのです」
「あ、いえ、そんな……」
ハハッ、と笑った客人に頭を下げながら、は膝を進める。そうして御膳を客人の前へ差し出すと、いそいそと部屋を出ようとする。
「時にお嬢さん。ひとつ訊いてもいいでしょうか」
え、と振り向いたに、客人は何かを思い出したように目を見開くと、背筋を伸ばした。
「失礼。名乗るのが遅れました。俺は煉獄杏寿郎と申します」
そう言って、座ったまま一礼をした。もつられて頭を下げると、
「です」
と、口早に名乗る。煉獄は口角を上げた。
「この村に、俺と同じような装いの男たちが来なかっただろうか」
「……知り、ません」
「そうか。では、この辺りで人が失踪した話を聞いたことは?」
「知りません」
かすかに震えるに、杏寿郎は「そうか」と静かに頷いた。
「……もう行ってもいいですか?」
「ああ。呼び止めてすまなかった」
は頭を下げ、部屋を出た。そうして廊下を進みながら、ばくばくと鳴る胸を叩く。
歳の頃はおそらく自分よりも五、六ほど上。濁ることのない瞳にまっすぐ見つめられると、思わず本当のことを言ってしまいそうになった。煉獄杏寿郎という客人が言った、「俺と同じような装いの男たち」を、は知っている。十日ほど前に、山へ向かう姿を見かけた。でも、「この辺りで人が失踪した話」は知らない。けれど、もしかすると、あの地下牢にいた子どもたちがそうなのではないか。あの客人は、一体何を探ろうとしているんだろう。
「おい」
びくりと肩を震わせて振り向けば、廊下の先に広がる闇の中から父がぬっと現れた。
「お父さん、あの方は一体?」
「あれは鬼様を狩ろうとしている邪悪な男だ」
「……鬼様を?」
鬼様。この村の神様。はその姿を見たことはない。けれど小さな頃から、母に寝物語として聞かされてきた。毎年の豊作は鬼様が厄災から村を守ってくれているからだ。鬼様がこの村に愛想を尽かしてしまえば、村の田畑は枯れ、飢饉が訪れ、村はたちまち崩壊するだろう。だから年に一度の祈年祭では供物を捧げて盛大に鬼様をもてなすのだ、と。
「お前、これであの男の寝首を掻いてやれ」
差し出された鎌に、は後退りをした。父は鋭い声で言う。
「家はこの村を治める一族。村の平穏を脅かすものは排除する。これは家の、お前の務めだ」
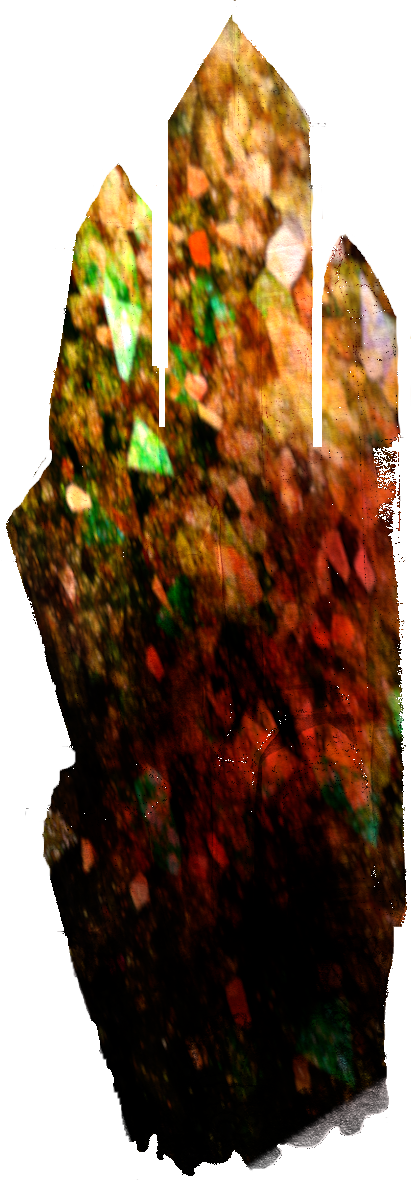
雨が降りはじめた。屋根を叩く雨音の勢いに合わせて、胸も激しく鳴る。襖の隙間から漏れていたあかりも消え、客人が寝静まった気配を察すると、は床板が軋まぬよう慎重に歩みはじめた。
そうっと襖を開け、中をうかがう。布団の上に、あの紅葉のような髪がちらりと見える。は音を立てずに中へと入ると、父から渡された鎌を両手で握りつつ、瞼を閉じて眠っている様子の煉獄を凝視する。そうしながら「やれる、やれる、やるしかない」と心のうちで呟いた。カタカタと震える指を鎮め、煉獄の喉元に向けて鎌を振り下ろさんとした時――。
「っ、あ……!」
衝撃に目を閉じたが次に瞼を押し上げれば、天と地がひっくり返っていた。畳の上で仰向けに転がり、手にしていたはずの鎌が自分の顔のすぐ真横に突き刺さっている。そして、両腕を圧迫されるような痛み。
「なぜだ。君はなぜ俺を殺そうとする」
目をやれば、煉獄がこちらを見おろしていた。その瞳は鈍く光っている。は煉獄に両腕を掴まれ、畳に押し付けられるようなかたちで彼を見上げていた。
「……この村の、ためです」
「俺がこの村に何をした」
「――しようと、しているんでしょう?」
「何をだ」
静かに燃えているような目が恐ろしくて、は顔を背けた。この村の神について部外者に話してはいけない。そんな村の掟を思い出し、奥歯をぐっと噛み締めて口をつぐんだ。煉獄はそんなの様子を観察するように見つめたのち、おもむろに口を開いた。
「俺は鬼殺隊という部隊に身を置いている。この世には鬼が存在していて、それは夜になれば血肉を求めて人を襲う。これまでに数え切れないほどの人々が犠牲になってきた。今もどこかで人が喰われている。俺はそんな鬼から罪なき人々を守るために生きている。君は?」
思いがけない問いに、は目を丸めて煉獄を見上げる。
「君は、何のために生きているんだ。この村のため? 御両親が隠そうとしている何かを守るため?」
は、この村のことしか知らない。この村に生まれた彼女にとって、村の掟は絶対、父や母の言うことは絶対だ。絶対的存在の彼らに存在を認めてもらわないと、この村で生きていけない。生きるために、認められたい。
「両親と……この村の人たちに、認められたいから……だから、生きてる」
か細い声で答えたを、煉獄は静かな目で見おろしている。
「認められないとこの村では生きていけない。俺には、そう聞こえるが」
「……ッ!」
は眉間に深く皺を刻み、唇をギリッと噛み締めた。煉獄の言葉が胸を突いたのだ。動揺する気持ちを悟られまいと、は煉獄の体や頬を手当たり次第に叩き、「どいてよ!」と叫んだ。体を退けた煉獄に、は身を転がしつつ立ち上がると、襖のほうへと駆ける。
「待て」
呼び止める声に、は目に見えない紐で引かれるかのようにぴたりと足を止めた。
「俺はもう行く。御両親には、すんでの所で逃げられたと伝えるといい」
そう言って、煉獄は自らの腕に鎌を当て、スッと刃を引いた。滴り落ちた血が畳や布団に染みていくさまに、は色を失う。
「これで君も少しは働いたと認めてもらえるんじゃないか?」
血の付いた鎌を差し出してにその柄を握らせると、煉獄は口角をきゅっと上げた。傷一つ付けられなかったと知れば、父はが怖気づいたと思うだろう。失望したと言うだろう。それを見越してなのか、煉獄は自ら鎌で腕に傷をつくり、血を滴らせて部屋を汚した。庇うようなその行動が、には気味が悪く思えて仕方がなかった。どうしてさっき知り合ったばかりの自分に、殺そうとした自分に、こんなことをしてくれるのか。この人はどんな見返りを求めているのだろうか。――いや、何を求めているのかなんて、そんなことは分かりきっている。鬼様の居場所だ。
「……私は、何も知りません」
その言葉に嘘はなかった。知っているのは山を住処にしているということだけで、鬼様がどこを寝ぐらにしているのか、詳細は何も知らなかった。
「君の口を割りたくてこうしたわけじゃない」
煉獄は眉を下げ、ふっと笑った。そうして羽織や衣服、刀を手に取ると、夜の闇へと消えていった。
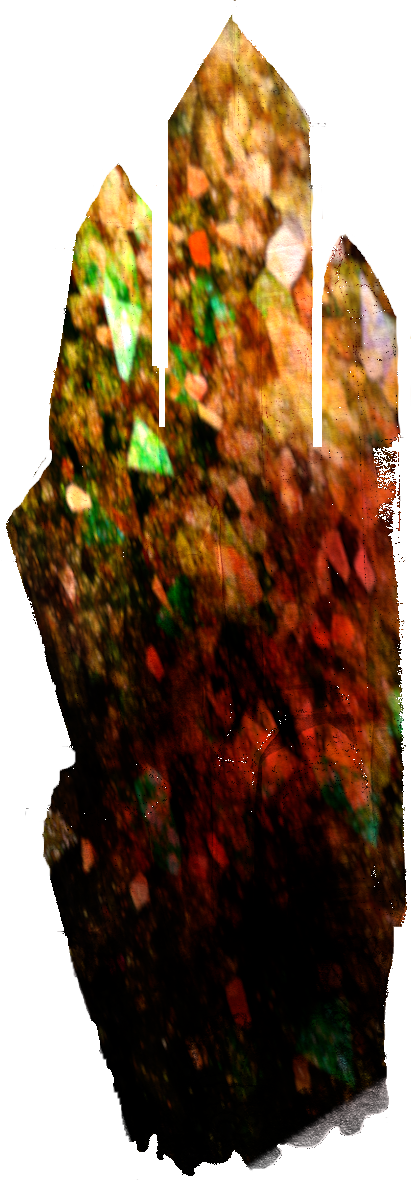
翌朝、は生贄を囲う洞窟にいた。客人をとり逃してしまったことを告げると、父は部屋の血痕を見て「傷は負わせたのだな」と低い声で言った。こくりと頷けば、父は力なく笑う。は許されたのだと思い胸を撫でおろしたが、次の一言に体を強張らせる。「俺の子どもたちならやれていた。所詮お前はこの程度だ」と。父は実子である兄弟たちを「俺の子どもたち」と呼んだ。はそこに自分が含まれていないことを、よく理解していた。ああ、いつまで経っても私は、この人たちの本当の子どもにはなれない。は「俺の子どもたち」という言葉を聞くたび、穴の奥深くに落ちていくような気になるのだった。
「うー、あー」
裾を引かれ、我に返ったように瞬きをしたは「何?」と足元で這う子どもに問う。言葉が分からない子どもは、うー、と何かを訴えるように唸っている。
「君にはごはん、あげられないの。ごめんね」
この子どもは、今度の祈念祭で捧げられる。今日この地下牢には一人だ。叔母は腰を痛めたとのことで来られなかった。そんな叔母から、「あの子は今日から儀式までの数日間、絶食させるんだよ。身を清めるためにね」と言い付けられていた。
他の子どもの食べ物を奪おうとしている生贄の子に、は厳しい声で叱る。そうして抱き上げると、他の子から引き離すために牢を移し替えた。恨めしそうに睨んでくる子に「だめ」と言えば、子は諦めたようにうなだれた。その様子を鉄格子の向こうから見つめながら、は自らの幼少期のことを思い起こす。
養子として育ったは、他の兄弟たちから冷遇された。母が見ていない隙に、お椀やおかずを奪わるので、幼い頃のはよく腹を空かせていた。なぜこんなことをするのか聞いたことがある。すると兄弟たちは言った。お前だけ飯の量が多くてずるいから、と。確かにのお膳に盛られる食事は、他の兄弟たちよりも量が多く、品数も多かった。母はよくに「お前は肥えなきゃいけないよ」と言った。そんな母だったので、が腹の虫を鳴らしていることに気づくと、団子や煎餅を与えた。そうしながら言うのだ、「お前はもっと肥えなきゃ」と。それを陰で見ていた兄弟には、その後もっとひどくいじめられた。一度体を暴かれそうになったことがある。泣き叫ぶの声に飛んできた父は、兄弟たちを張り倒し、厳しく折檻した。母はの股を確認し、父に「大丈夫」と言った。未遂に終わったが、父はそれから夫婦の居室の隣部屋にを寝かせるようになった。はこのときに察した。両親が他の兄弟たちには求めず、自分にだけ強く求めていることがある。それは、ふくよかであること、純潔であること。この二つだ、と。かわいさゆえに、ではない。両親が自分のことを心から家族として認めているわけではないと、肌で感じていたからだ。ではなぜ、自分はここまで不自由なく育てられてきたのか――。
「あ、あー」
鉄格子の向こうにいる子どもが、なぜだか幼い頃の自分と重なるように思えた。
「君は鬼様に捧げられるんだよ。もうじき楽になれるから。お腹が空くことも、さびしい思いをすることも、もうないからね。だからもう少しだけ、ここで頑張ろうね」
が格子の間に指を差し入れれば、子どもはそれをちゅぱっと口に含んだ。お乳だと思ったのだろうか。この子の母親は、どこにいるんだろうか。
「やはりいるんだな。この村には、鬼が」
洞窟内に響いたその声に、は弾かれたように立ち上がる。振り返り、松明のあかりが届かない暗がりの方を凝視する。次第に近づいてくる足音。
「この村では鬼を神として祀っているんだな。だから“鬼様”か。その子どもたちは、差し詰め鬼への供物というところか?」
暗がりの中から姿を現した煉獄に、は拳をかたく握り、ギリッと睨みつける。
「君は知らないと言ったな。何も知らないと。だが君は今こうして、この村の悪しき風習に加担している」
「……悪しき風習?」
「罪のない子どもたちを鬼に喰わせて五穀豊穣を祈るなど、許されていいことではない」
どうして祈念祭のことを知っているのだろう。は眉根を寄せる。煉獄はその表情から彼女が何を問いたいのか察したようだった。
「君の家を去ったあと、この山の向こうにある里へ向かった。そこにはこの村のことをよく知っている高齢の女性がいて、仔細を教えてもらったんだ」
「そんなこと……村の話は他言無用なのに、どうして……」
言いながら、煉獄は一歩、また一歩との方へと近づいていく。彼女は俯き加減で、どうして外部の人が村の内情を知っているのかと思案に耽っていたので、近寄ってくる煉獄の影に気づかない。
「娘がこの村に嫁いだと言っていた。その娘から村のことを伝え聞いたと。けれど生まれた子どもを一度見せに来て以来音沙汰がなく、もう十五年ほどが経つと」
ハッと顔を上げたは、もうすぐ目の前まで迫った煉獄の姿に後退りをする。煉獄はなおも歩みを止めずに距離を詰めていく。
「孫娘は生きていれば十五。赤ん坊は色白で、髪の色味が薄かったと言っていた。……不思議だな」
「なに、が――」
「君と同じだ」
の後退する足が止まった。目を見開く彼女を、煉獄の焔色の瞳がまっすぐに捉える。
が口を開きかけたとき、洞窟内に子どもの泣き叫ぶ声が響いた。牢の中に閉じ込められた生贄の子が、顔を赤くしながら泣いていた。腹が空いて堪らなくなったのか、それともと煉獄の間に流れる殺伐とした空気を察して恐ろしくなったのか。
牢に向かおうとする煉獄の前に、が立ちはだかる。
「何も知らないくせに……邪魔、しないでよ」
「この村は祀るものを間違っている」
「鬼様は村を守ってくださってるの。どうして狩る必要が?」
「どうして? この子どもたちを見てもそう言えるのか」
言われて目線を下げれば、口の周りをおかゆで汚す子どもらがを見上げていた。牢の向こうでは生贄の子がしゃくり上げている。は見たことがないから知らないのだ。人が鬼に喰われる様が、いかに酷たらしいかを。
「想像してみてほしい。生きたまま皮膚を破られ、肉を裂かれ、骨を砕かれながら泣き叫ぶこの子たちの姿を。そのうち声を上げることすらかなわなくなり、虚空を見つめたまま息絶えていく。鬼は目玉の一つも食いこぼさないから、その場に残るのは骨だけだ」
煉獄は牢の戸を開け、子を抱き上げた。子どもは煉獄の髪を一房手に取り、毛先を口に含んだ。煉獄は子どもの背中をあやすように叩きながら、眉を震わせているを見やる。
「君は“家族”を人質に取られているんだな。だがその“家族”は虚像だ。残念だが、君が求めているものはこの村にはない」
そうして煉獄は、訳が分かっていない様子で口をぽかんと開ける他の子どもたちも連れ、洞窟の出口へと向かっていく。は非難の声も上げず、制止しようとするわけでもなく、暗がりに消えていくその後ろ姿をただ目に映していた。
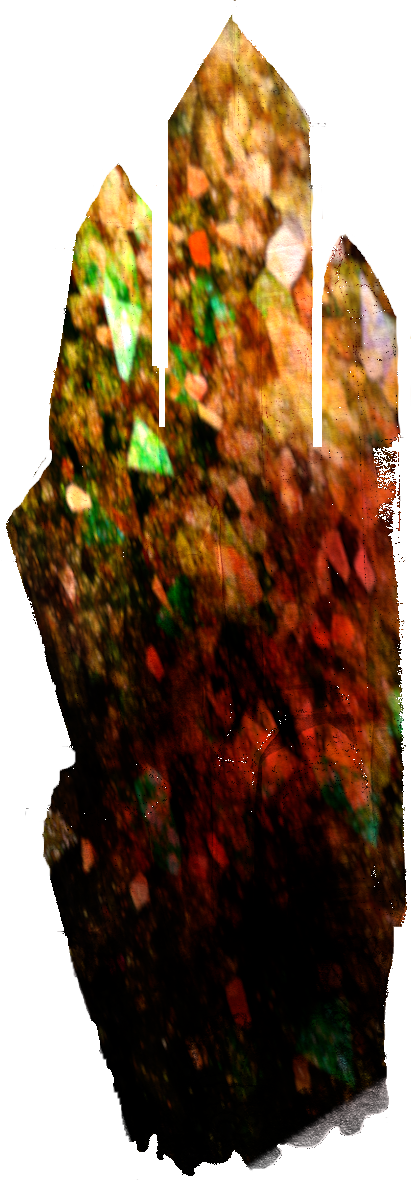
地下牢の子どもたちが消えたことは、の口から家の家長である父に伝えられた。あの客人、煉獄杏寿郎が子どもたちを連れ去った。その話を聞いた父は憤怒した。母はたじろいだ。
生贄を捧げる祈念祭が迫ったある晩、部屋で眠っていたは頭に鈍い痛みを感じて起き上がった。一瞬、母の顔が見えたような気がした。しかし再び頭に衝撃が走り、視界が暗転する。そうして次に目を覚ましたがいたのは、自室の布団ではなく、洞窟の牢内に敷かれた筵の上だった。見れば、鉄格子の向こうには父がいた。父は言った。村で話し合った結果、今年はお前を鬼様に捧げることになった、と。これは罰なのだと思った。生贄の子どもたちを連れ去られてしまったことの罪を、その身をもって償えと言われているのだと。しかし父は言った。これは光栄なことだ、と。この村から子どもがいなくなった今、鬼様に捧げられるのは処女だけ。つまりお前だけだ。この村のために務めを果たしてくれるよな――。
父が去って一人きりになると、は震える体を鎮めるように膝を抱き寄せた。光栄なことだと言われたが、ちがう。生贄の世話をしてきたからこそ知っている。ここには恐怖しかない。
「なんで、私が」
あの男さえいなければ私がこうなることはなかった。煉獄杏寿郎。憎い、憎い。あの男が憎い。
はぎりぎりと唇を噛む。じんわりと血が滲んでいた。煉獄を憎むと同時に、光栄であるはずの生贄の役目を避けようとしている自分にも嫌悪した。
洞窟から連れ出した子どもたちを山向こうの里に預け、煉獄は再び村へと潜入する。子どもたちの件で、彼女が責めを負っているかもしれない。里を治める家の近くまで向かう途中、農作業中の村人が話しているのを漏れ聞いた。「ついにあの子が今年の供物に」という言葉に、杏寿郎は踵を返して洞窟の方へと向かうのだった。
「生贄に選ばれました。身に余るほどの大役です」
牢の向こうには身を小さくさせる彼女がいた。こちらに気づくと、ゆらりと顔を上げた。
「あなたのおかげ。ありがとうございます」
力なく笑うに、煉獄は目を見開いたまま問う。
「なぜ君が。子どもだけではないのか?」
「処女だから。身の清い人が捧げられる慣わしなんです。子どもがいなくなった今、この村で唯一の純潔である私が、鬼様に……」
は天を仰ぎ、ははっ、と笑い声を漏らした。狂いかけている。そう察した煉獄は、牢を破り彼女の腕を掴む。やめて、と振り払おうとするその力は、かなしいほどに弱々しかった。
「私だけなんです! もう、生贄になれるのは……私がいかなきゃ、この村は厄災に見舞われてしまう」
「鬼こそが厄災だ。鬼がいなければ君がこんな思いをすることもない」
「そんなっ、そんな、こと――」
「では処女じゃなくなればいい」
煉獄の言葉に、は眉根を寄せた。「どういうこと?」という彼女の声は、煉獄の羽織の中に消えた。煉獄は彼女を抱き、そのまま筵に倒す。白い首筋に指先を這わせると、彼女はびくりと体を跳ねさせた。煉獄がふとその顔を見やれば、
「……っ」
彼女は、声を押し殺して泣いていた。体は小刻みに震えている。煉獄は手を止め、「違う」と呟く。
「こんなことは間違っている。すまなかった。君が鬼のために何かを失うのは、違う」
煉獄はを助け起こす。は手のひらで顔を拭いながら、煉獄を見上げる。
「君は何も失うべきじゃない」
ずしりと腹に落ちるような力強い声に、言葉に、は唇を震わせた。
涙が溢れて体が震えたのは、幼少期に兄弟たちから犯されそうになった記憶が蘇ったからだ。煉獄がそうしようとしたのは、自らの欲望からではなく、自分を救おうという思いからだということは、分かっていた。
――いつだって何かを奪われてきた気がする。
父は村のために命を捧げろと言った。養子とはいえ今まで十五年も共に暮らしてきたのに、そう言う父の顔にはなんの迷いも悲しみも滲んでいなかった。それに、居室で頭を殴り意識を失わせたのは母だったと、は気づいていた。捧げることを求められてきたにとって、煉獄の言葉は痛いほどに深く突き刺さった。
「一刻も早く根源を断つべきだ」
煉獄は腰の刀を握る。炎を象った鍔を目に映していたは、不意に「それは」と声を漏らす。
「この刀か?」
「いえ、その手……」
煉獄は自らの左手を見つめる。手の甲に何かが書かれていたのだ。「ああこれは」と煉獄は微笑する。
「ここにいた子どもたちを他所へ移したとき、なかなか俺から離れようとしなくてな。おそろしい絵でも描けば離れるかと」
「……おそろしい?」
「そのつもりだったが、彼らにはそうは見えなかったようだ。もっと描けとねだられてしまった」
煉獄は眉を下げて笑う。手の甲には、目を怒らせた蛸のような生物が描かれていた。まじまじと見つめるに、煉獄は力を込めて言う。
「みな無事だ! 今は安全な場所で匿ってもらっている」
は唇をぎゅっと結んだ。この悪臭漂う薄暗い洞窟で這っていた子どもたちが、陽のひかりのもとで無邪気に笑っている像が浮かんだのだ。その途端に、込み上げてくるものを抑えきれなくなった。
「……よかった、ほんとうに、よかった」
こんなことは間違っている。それは、初めてこの地下牢で子どもたちを見たときに感じたことだ。けれど両親の言葉や村の掟に縛られたは、感情や思考を押し殺すしかなかった。
「この村に子どもたちの未来はない。君もそうだ、」
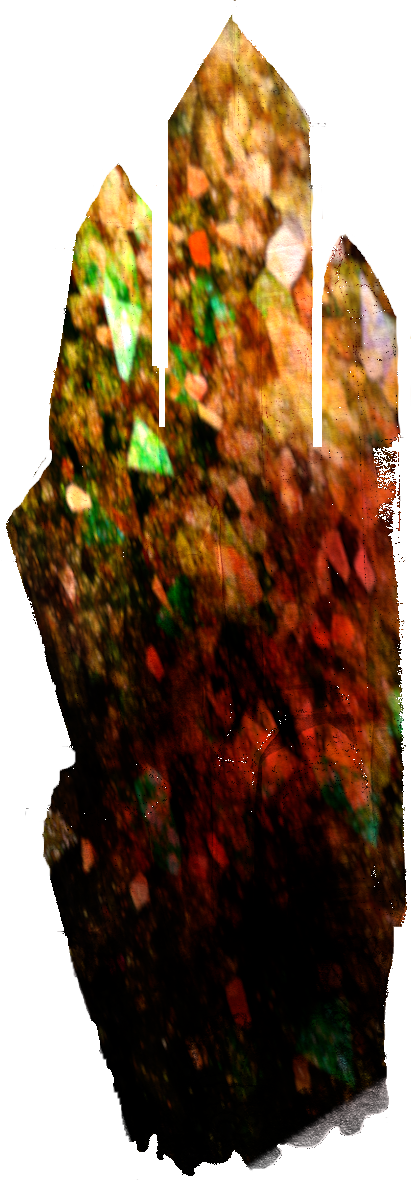
その山には踏み入ってはいけないと教えられてきた。鬼様の神聖な山だから、と。
は煉獄を連れ、そんな鬼の棲む山を登る。道中には人骨が転がっていた。近くにあった刀や服を手に、煉獄は「全滅か」と呟いた。
険しい山道だった。絶食をしていたため体力が落ちているは、煉獄に渡された棒を杖がわりに進む。
「煉獄さん。山の向こうの里に、この村のことをよく知るおばあさんがいると言いましたよね」
「そうだ」
「娘がこの村に嫁いだ、孫娘は生きていれば十五ほどだと」
「ああ」
「つまりそれは、私のことだと思いますか?」
息を上げながら訊くに、煉獄は迷いなく答えた。
「俺はそう確信している」
「……そう、ですか」
は道の向こうを見て「もうじき山頂です」と言った。そうしながら思っていた。では、生みの母はどこにいるのだろうと。これまで実母や実父について両親に尋ねることはなかった。聞いてしまえば、家に不満があると受け取られてしまうかもしれないと思ったからだ。ただ漠然と、自分は捨て子なのだと思ってきた。だから、もう捨てられないようにと両親の顔色を伺いながら生きてきた。
「山頂に鬼はいないはずだ。もう少し陽を遮る場所……洞穴はないか?」
「洞穴、ですか。私はこの山に詳しくなく――」
の声はそこで途切れた。襟首を掴まれ、ぐいっと後ろに引かれたからだ。そのまま体が浮き、上へ上へとのぼっていく。
「マレチ、マレチ、ダ」
大木の枝へと吊るされたは、おそるおそる声の方へと目を向ける。白髪で白い目、黄ばんだ歯は獣のように鋭く、熊のような体躯の――鬼だ。鼻をつく異臭。荒い息。その口から流れる涎。は「煉獄さん」と震える声で漏らし、地上を見おろす。そこには刀を構えた煉獄が、自らをぐるりと取り巻く松明を鋭い目で見据えていた。村人だ。手に斧や鎌、鋤を持って煉獄を取り囲んでいる。
「ショジョ、マレチ、ウマイ」
鼻をすんすんと鳴らしながら近づく鬼に、は身震いした。
「……れ、ん、れん……っ、煉獄さん!」
助けて。の声に、煉獄は目だけを上に向けた。と煉獄の視線が重なった、次の瞬間。の体が揺れる。彼女が吊るされていた木の枝を、煉獄が断ち切ったのだ。太い枝と鬼の巨体が、地上にいる村人へ向かって落ちてゆく。悲鳴と衝撃音が上がるなか、の体を抱えた煉獄は、そのまま木から木へと飛び移りながら山を登っていく。
山頂に着くと、煉獄はを下ろし「怪我はないか」と訊いた。
「大丈夫です。ありがとう、ございます」
「俺は鬼の頸を斬る。君はしばらく――」
「」
ひどく落ち着いた、けれど鋭さを孕んだ声。はゆっくりと振り返る。その人の姿を見る前から、この声が誰のものかは分かっていた。
「なぜ私やお父さんの言うことが聞けないんです。なぜこんな罰当たりなことをするんです。あなたを育てた私たちに対して、お前はなんてことを。恩を仇で返すなんて」
ゆるさない。許さない、許さない、許さない。
の母は念仏のようにその言葉を繰り返した。煉獄は一歩踏み出したの肩に手を置き、かすかに首を振った。しかしは煉獄の手をそっと離すと、ぼそぼそと呟く母を見据えた。
「お母さん」
「許さない許さない」
「お母さん、私の本当のお母さんは今どこにいるの?」
その問いに、養母は呟くのをやめた。そうして血走った目をに向けると、
「死んだ。お前の母親も父親も、殺されたよ」
そう言って、にちゃあっと口を広げて笑った。
「逆らうほうが悪い。お前は生まれながらいっとう上等な鬼様の供物なんだ。だってお前は稀血なんだから。捧げろと言われたら財産でも子どもでも捧げるのがこの村の掟なのに、あの親が逆らうから殺されたんだ。捧げないなら奪うまでのこと」
養母はへと近づくと、小刻みに震えるの頬を撫でた。
「お前は最初から鬼様に捧げるつもりで育ててきた。鬼様は年頃の処女の血肉がお好みだから、この歳までお前を……なのに、こんな……許せない、このままじゃあ村が……許せない、許せない」
ギリッと頬に突き立てられた爪。養母は手当たり次第にを引っ掻くが、は反応を示さなかった。呆然と立ち尽くし、焦点の定まらない目で空を見つめている。
「この男がお前を誑かしたのかい」
引っ掻き回す腕を掴んだ煉獄に、養母は憎々しそうな目を向けた。そうして「この罰当たりが!」と奇声を発しながら、養母はもう片方の腕で煉獄に掴みかかる。煉獄はそれを交わしつつ、養母の両腕を拘束する。なおも暴れる養母に煉獄は「失礼」と、その後ろ首を手刀で打った。
意識を失った養母をその場に寝かせていると、「おい!」と怒声が飛び込む。の養父や村人たちが、松明を片手に山を登ってきたのだった。地面に横たわる妻には目もくれず、養父はを指して言う。
「戻れ。お前しかいない、この村を救えるのはもうお前しかいない。鬼様に、鬼様の一部になってくれ」
煉獄は刀を構え、村人たちのほうを見据えていた。けれどその焦点は村人たちではなく、その背後の山中に広がる闇へと当てられていた。その暗がりから叫び声が聞こえる。そのさまに、煉獄は眉をぴくりと動かす。誰かが喰われたのだ。
「煉獄さん」
闇の中からゆらりと姿を現した鬼。その口からは血が滴り、手には村人の首がぶら下がっていた。煉獄は眼光鋭く鬼の動きを監視しながら、の言葉に耳を傾ける。村人や養父が騒ぎ立てる声などまるで聞こえていないかのように、は煉獄の背後に立つと、言った。
「殺してください。あの鬼、殺してください」
煉獄とに向けられていた村人たちの怒号は、仲間の首を見た途端、阿鼻叫喚に変わる。煉獄はを見やり、うんと頷く。
腹が減って仕方がない鬼は、逃げ惑う村人を捕まえようと獣のように四つん這いで追い回す。養父の背に鬼の鋭い爪が届きそうになったとき、煉獄の刃が空を斬った。闇夜に火の粉が舞うかのようだった。ごとりと地に転がった鬼の頭。養父は絶叫した。それに続き、村人たちも声を上げ、「祟られる」「みんな死ぬ」と恐れ慄く。
「行こう」
刀を鞘に収めた煉獄が、へと手を差し出す。は足元に横たわる養母、鬼の頭を胴体と繋げようとする養父を見やり、力なくうなだれた。彼らはを娘として迎え入れたわけではなかった。いつか鬼に捧げる供物として、育てていただけ。それも、の実の両親を殺して、奪ったのだ。それでも今日の今日まで、この村だけが生きるすべてだったにとって、今夜突きつけられた現実をすぐに呑み込むのは難しかった。
そんな彼女の肩に、煉獄がそっと手を置く。
「言っただろう。ここに君の未来はない。それに、外では君の本当の家族が待っている」
本当の家族。その言葉に、は顔を上げる。煉獄は山の向こうを指す。そこは、蛍のあかりが集まったかのようにぽうっと輝いていた。里だ。の実母のふるさと。血の繋がった祖母が待つ集落。
「……私だって、気づいてもらえますかね」
「他人の俺でも分かったんだ。君のお祖母様ならば一目で気づくはずだ」
大丈夫。その力強い言葉が、の背を押した。
煉獄とともに山を下りはじめたに、養父の「裏切り者」という悲痛な声が向けられる。しかしは振り返らなかった。この村こそが厄災であると、知ったから。

或る村
― 完 ―
冒頭の詩は金子みすゞ著「ほしとたんぽぽ」より引用