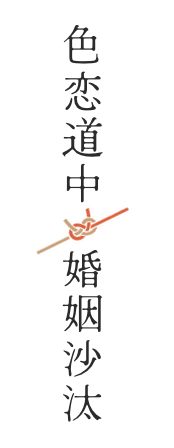
沈む星ぼし
海を見に行かないかと聞かれて、是とうなづかざる得なかったのは、まさに周囲の口出しの賜物であった。男はまんじりとして、向かいの座席でまどろんでいる。車窓から吹き込む風が彼の前髪を揺らすと、まぶたをくすぐったそうに撫ぜた。
やがて列車が駅につくと、駅のちかくでは蕎麦だしのいい匂いがただよっていた。空腹の表情をする男をいざなって、蕎麦屋ののれんをくぐる。右手を亡くして一年がたつので、男はもう器用に左手で箸をつかう。ずるずるとすすった蕎麦は、芳醇なにおいがした。熱いものを食べて、すんっと鼻をすする男は、まるで幼子のようだ。懐に入れていたちり紙を渡せば、小さく礼を言って鼻をかんだ。
きっかけは、屋敷を訪れていた元音柱が奥方たちと一緒に鎌倉へ行った、江ノ電に乗ったと冨岡へ話したことだった。冨岡は興味深げに話を聞き、聞き終わると「俺たちも行こう」「海を見に行かないか?」などと言いだした。やんやと宇髄様ははやし立て、留守は任せろなどというありさまで、誰か止めてほしいと思っても誰も止めてくれなかった。
冨岡の屋敷にやっかいになり、もう半年以上が経とうとしている。責任を取るという言葉の元に、刀鍛冶の里からさらわれるように連れてこられ、何度か里へ戻ることを画策したが、今ではすこし諦めている。刀を打つことも研ぐことも好きであったが、彫金仕事も好きであったし、冨岡はわたしが鍛冶をするための小屋を屋敷の庭に建ててくれた上に、邪魔をすることもない。里でいい加減に嫁に行けと言われ続けるよりかは、きっと快適な暮らしであった。
硝子窓はなく海風にさらされ、冨岡とわたしは適当な駅で電車を降りた。同じ駅で降りた人の話を聞けば、極楽寺がちかくにあるのだという。夕暮れも近づく時間、冨岡はすんと鼻を鳴らすと海辺へ向かって歩き出す。暮れ始めた空の青が好きだった。道行く人はみな海辺から引き上げるようで、わたしたちはそれに逆らって歩く。
前を行く冨岡の背中は、左側の重心が少し下がっている。いつも重い刀を腰に差していた名残だ。
浜辺につけば、暮れかけの海には人はまばらで、五月といえど肌寒く感じる。てのひらをこすり合わせると、それに気づいた冨岡が羽織を渡してきた。おとなしく受け取り羽織れば、藤の花のにおいがした。
風をよけて岩陰に座り込む。人気がすくないことも相まってひどく心ざむしいような心地がした。海を見るのは、故郷から出てきて以来だからだろう。ひっきりなしの波の音が、耳の奥までざわめかせる。
「疲れたのか?」
「少し。はじめて来た場所なので」
「そうか。俺は任務で何度か訪れたことがあった。疲れたのなら、少しこちらに寄りかかっているといい」
横の冨岡はわたしをひんやりと見下ろしながら言い、目線を前に戻した。わたしは抱えた膝に頭を乗せ、ざやざやと騒がしい波の音を聞く。刀鍛冶の里は山奥にばかりあったので、波の音も潮の臭いも馴染みないものだ。
すん、と鼻を鳴らせば身じろぎした冨岡がわたしの肩を抱く。そこに軽蔑するようないやらしさがあればいいのに、驚くことに、そこにあるのは気遣いでしかなく、わたしはいつも嫌になってしまう。裸の体を暴かれることも、にやついた目線で犯されることも、下品な言葉に踏みにじられていくわたしの心も、それは既知のものであったのに、冨岡の手のひらの温度はそれを知らない。冨岡はただ寒かろう、とわたしの肩に左手を回し、いまだにしなやかな筋肉のつく腕で肩や背中を温めてくれる。
じん、と熱い涙が目頭に浮かんで、感傷的すぎると必死で飲み下した。絶対に、顔をあげるもんか。そう思った。
まどろみから浮き上がれば、夜はとっくに更けていた。いつの間にか冨岡の腕の中で抱きかかえられており、背中に彼の体温が感じられる。びくりと震えれば、「すまない」と小さな謝罪が降ってきた。
「いいえ。眠ってしまったわたしが悪いので」
「ここは寒い、もう少ししたら、行こう」
冨岡は言い、海辺を指さした。黒いさざなみが寄せて返すのに、その端がちらちらと青く光っている。まるで頭上で光っている星ぼしが落ちて、海に溶け込んだようだった。
目の前の美しい光景に目を見開けば、すこし笑ったようなそぶりの冨岡が「海蛍だ」と教えてくれた。蛍とは別種だが、そういう小さな虫の類がいるらしい。
砕いた星の屑が、波間に連なるかのようにちらちらと光っている。東京では電飾で建物を飾り付けたりするのだという。それもこんな景色なのかしら。すこし興奮してみていれば、背後の冨岡が背中ごしで笑ったのがわかった。
「昔きたときも、こんな光景だった。藤家紋の者に聞けば、海蛍だと。
宇髄に話を聞いたときに思い出して、見せたいと思った」
ぽつぽつと話す冨岡はすこし嬉しそうで、わたしはくちびるを噛む。背後から肩を抱く腕は熱く、それに縋りたくなってしまう。お前が満足するまで見ていよう。そういう冨岡はいつも、わたしの都合しか考えてくれない。
海蛍がちやちやと、黒い海の中で星のように光る。時折浅瀬の遠くのほうで、よく似た光が浮かんでは、海に吸い込まれて消えた。気のせいか、きゃらきゃら幼子の笑い声が聞こえる。
ふと思い出したが、鎌倉には水子供養の寺があると聞いた覚えがある。笑い声を響かせながら海に溶けたあの光は、幼子の魂とでもいうのだろうか。
「……行こう」
「もういいのか?」
「はい、もういい」
砂に足を取られながら立ち上がろうとすると、冨岡が手を取って支えになってくれた。体幹のいい冨岡は、なんでもないことのように一人で立ち上がり、歩き出す。宿はどこだろうかなどと、とぼけたことを言う冨岡の後ろを歩きながら、海辺を振り返る。
海に溶ける生きられなかった幼子の魂があるとするならば、先を行くこの男の魂は一体何に溶けるのだろうか。そんな、詮のないことを考えた。